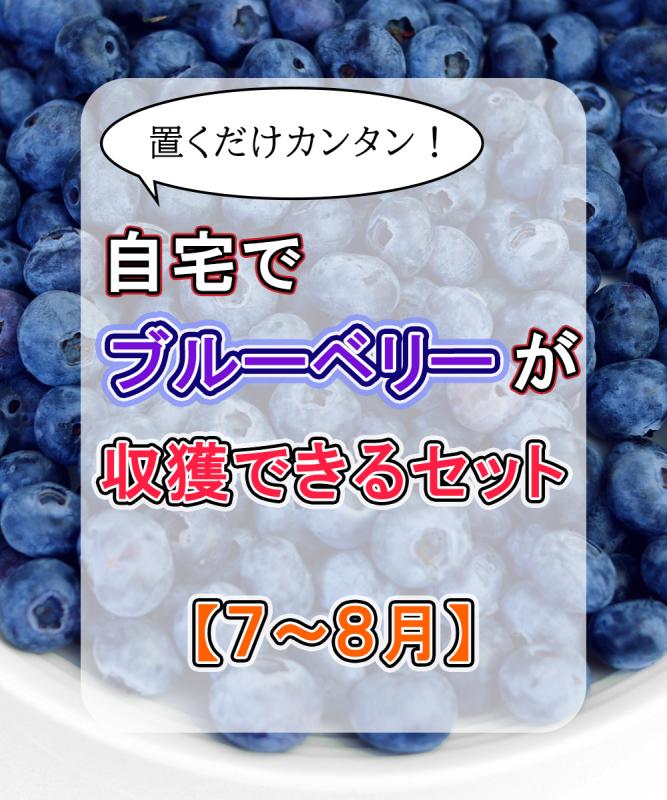【忙しい方におすすめ】初心者でもできる梅の栽培方法
家庭菜園でできる梅の育て方

梅は数ある果樹の中でも管理作業が少ないため初心者の方でも育てやすいことや、実を梅干しや梅酒、ジュースに加工して楽しむことができるので庭木として大変人気があります。
しかし、実際に庭で梅を育てるとなると、
「私の住んでいるところで育てることができるの?」
「庭の広さはどれくらい必要?」
などいろんな疑問が出てくると思います。
そこでこの記事では、
・育てる前に知っておきたい梅の特徴
・梅を育てるために最低限必要な管理作業
をご紹介していきます。
また、梅栽培のプロである梅農家さんにも直接コツを聞いてきました!
ぜひ梅栽培の参考にしてください。
目次
育てる前に知っておきたい梅の特徴
他の果樹と比較して手間がかからない
梅の管理作業はほかの果樹と比較して少ないため、栽培に手間がかかりません。
1年間の管理作業は冬の剪定、収穫雨の枝の間引きさえしてしまえばあとは収穫するのみ。たったこれだけで毎年梅の実を楽しむことができます。
梅は普段仕事や家事で忙しい方にピッタリの果樹といえるでしょう。
寒さに強い
梅を育てるには年平均7℃以上の気温があれば大丈夫です。さらに耐寒気温は-15℃なのである程度寒い地域でも育てることができます。
梅の品種の一つである豊後(ぶんご)はさらに耐寒性が強く東北地方でも育てられているので、寒冷地に住んでいる方におすすめ。
小型のきれいな花を咲かせる

梅は花、香り、果実の3拍子がそろった木としても有名です。2~3月に開花期を迎え、小さくかわいい花を咲かせてくれます。
きれいな花はお庭を華やかにしてくれるので、梅はシンボルツリーとしても最適です。
梅の植え付けと仕立て
梅の植え付け(11~2月ごろ)
梅の植え付けは休眠期の11~2月ごろの間に行うのがベストです。
・鉢植え
鉢底に鉢底石を入れ、土を鉢の半分程度入れます。
そこに苗を根を広げながら入れ、さらに上から土をいれます。
この時、接ぎ木の部分(木根元のこぶ状にプクッと膨らんだ部分)を土に埋めてしまわないように、地上に出して植えるよう注意します。
次に、苗の主幹を1/3程度切り詰めます。
こうすることで春以降に勢いのよい枝を伸ばすことができます。
最後に水をたっぷりやれば植え付けは終了です。
・露地植え
植え付けの1か月前くらいに直径70cm、深さ50cm程度の穴を掘り、堆肥、石灰、有機肥料を適量混ぜ、埋め戻します。
1か月後、苗木を根を広げながら浅めに植えつけ、鉢植えと同じように主枝を切り詰めたっぷりと水をやれば完成です。
梅の仕立て方
鉢植え、露地植えともに「変則主幹形仕立て」がおすすめです。
変則主幹形仕立てとは、最初は縦長に仕立て、木が高くなったら主幹を途中で切り戻し、側枝を伸ばし樹形を低く保つ方法です。
他には「開心自然形仕立て」でも育てることが出来ます。
開心自然形仕立ては、骨格となる枝を株元の低い位置から2~4本発生させ、樹高が低くなるようにひもなどで枝を斜めに誘引する方法です。
2種類とも木を低く保つ事ができ、作業がしやすくなるので家庭菜園におすすめの仕立て方です。
梅の周年作業
水やり

・鉢植え
水やりのタイミングは、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るくらいまでたっぷり水をあげましょう。
水やりには水の補給以外に、土の中の空気や養分を交換する大切な役割もありますので、十分な量の水をあげる必要があります。
・地植え
地植えで育てる場合は基本的に水やりは不要です。
根が地中に広い範囲で広がり、そのうえ地中にはある程度雨も保水されているためです。
ただ、晴天の日が何日も続き土が乾いてしまうと水切れを起こし、その後の実つきが悪くなってしまうことがあります。
土の状態をよく観察し、必要に応じて水をたっぷりあげましょう。
肥料
1年の間に元肥、追肥、お礼肥の3回に分けて施します。
一度に大量に肥料を施しても、根が傷むか、吸収されないうちに根の範囲外に流れ出てしまうからです。
休眠期の11月に元肥として、ゆっくり効果の持続する有機質の肥料、4月に果実肥大を助ける追肥として化成肥料(チッソNーリン酸PーカリK=8-8-8のものなど)、収穫後に消耗した木に養分を与えて回復させるお礼肥として化成肥料を施すのが一般的です。
梅の管理作業
枝の間引き(5月中旬~6月)

冬の剪定だけでは枝数をコントロールするのが難しいので、初夏にも枝を間引きます。間引くことで風や日光がしっかり当たるようになり、枝が充実するので花芽たくさんできるようになります。
枝が混んで葉が触れ合わないように間引いていきます。間引くときは枝の付け根から切るようにしましょう。
収穫(5月中旬~7月中旬)

収穫適期になったら、軽くつまんで上に持ち上げるようにして収穫します。
梅は高温乾燥に弱いので、保存する際はポリ袋に入れて冷蔵庫に入れて保存すると良いでしょう。
収穫:農家さんのアドバイス

梅は用途によって収穫適期が変わります。
梅酒やジュースにする場合は果汁の多い青梅を収穫するのがおすすめ。果実の肥大が止まり、表面の毛が半分程度落ちたときが適期です。
梅干しにするなら黄梅が最適。青梅の状態からもう少し待つと、香りが豊かになり果肉が柔らかくなった果実を順次収穫していきます。
せっかく食べるならおいしく食べたいですよね。「何に使うか」で収穫時期を調節してみてくださいね。
剪定(11月下旬~1月)

梅の木が休眠期になったら翌年のために剪定作業をしておきます。
「桜切る馬鹿、梅切らぬ馬鹿」という言葉があるように、剪定は梅の管理作業の中で一番大事と言えるでしょう。
最初は慣れないかもしれませんが、やっていくうちに分かってくるので、根気強く続けていきましょう。
剪定する場所と順番は以下のとおりです。
①交差している枝や、混み合った枝、枯れ枝、下向きになった枝など不要な枝を切る
②30cm~50cmの枝の先端を1/4程度切り詰める
③先端の枝を1本に間引く
梅は枝が古くなってくると実付きが悪くなってきます。5~6年を目安に「切り替え剪定」をして、枝を更新するようにしましょう。
切り替え剪定をする時は、枝の外側に芽が付くように切ってくださいね。
また、枝は切ったところから枯れ込んだり、病原菌が入ってしまい生長に影響が出てしまう恐れがあります。
それらを予防するために、太い枝を切った場合には、切り口に癒合促進剤を塗るようにしましょう。
農家さんのアドバイス
梅の実がなりやすいのは5~15cmの短い枝です。30cm以上の長い枝には花が咲くだけで実がつきにくい傾向があります。
②で30cm~50cmの枝先を1/4程度切り詰めることによって、切り詰めた枝から短い枝をたくさん発生させることができます。
選定は翌年の収量を決める大事な作業です。最初のうちは枝の長さを確認しながら剪定していきましょう。
必要に応じて行う作業
人工授粉(2~3月)

毎年のように実付きの悪い場合は、人工授粉をしてあげると実をつけてくます。同じ品種では受粉してくれないので、違う品種同士で行ってください。
咲いている花を摘んで、異なる品種の花にこすりつけてください。この時開花直後の花や、花びらが落ちてしまっている花につけても効果がないので注意しましょう。
摘果(4月中旬~下旬)

大きい実を収穫したい場合は摘果をすると効果的です。傷のあるもの、形の悪いものを優先的に取り除くとよいでしょう。
まとめ

仕事や家事、育児に忙しい方は、果樹を育てようと思っても管理作業が多いとどうしても後回しにしてしまいがち。気づけばどうしようもなくなった…ということもあるでしょう。
しかし、梅は管理作業が簡単かつ少ないので、負担なく育てることができるはず。
ぜひ庭木にして、梅のある生活を楽しんでくださいね。















.jpg)