雑草に振り廻されない!わが家の雑草対策
雑草という見方を変えて、前向きな除草をしよう!

散歩中に開花している雑草を見かけると、儚げでたくましく感じ思わず心で応援したくなります。
しかし、丹精込めて作った花壇に同じ雑草が生えてくると、そのまま放置した時の悲惨な状況や億劫な雑草管理を考えてしまいモヤモヤしてしまいますよね。
同じ雑草なのに、自分に都合が悪くなると雑草という邪魔者扱いのレッテルを貼ってしまうのです。
それなら、雑草に対する見方を変えて自分に都合が良い雑草にしてみませんか。
自宅にお庭がある以上、雑草対策は毎年の作業になります。
生命力の強い雑草を上手に取り入れればストレスのないお庭管理が実現できますよ。
そこで、私が日頃行っている雑草対策をご紹介いたします。
この記事は、お忙しい方のために
目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。
詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか
気になる小見出しをクリックしてみてください。
目次
わが家の雑草対策
雑草を雑草と思わない

草花を見て「雑草」と認識するのは、自分に都合が悪い時と景観性が悪い時ではないでしょうか。
その後の労力を想像するだけでも気が遠くなりますよね。

しかし、植えた覚えもないバラの花があたり一面に咲いても雑草という認識はないですよね。
自分にとって都合がよく景観性が良いからです。

そこで、自分にとって都合が良い雑草にする為に、まずは雑草の葉の大きさや形、どの位の高さになるのか、花や種をつけるのか観察しましょう。
自宅敷地内の雑草であれば、東西南北の様々な環境に適した雑草が同じ場所で毎年生えてくるので何となく記憶の中にイメージが残っているのではないでしょうか。
①-1625384938.jpg)
例えば、細長い葉の植物周辺に丸い葉の雑草が生えれば葉の形の対比でそれぞれの植物の魅力が引き出せます。
雑草の代表選手であるカタバミも可愛らしい葉の形をそのまま生かすという選択もあるんです。
また、根っこがしっかりしていて抜きにくい雑草等も、逆に考えればしっかりとした根っこが土止めになるということです。
ネガティブ要素をそのまま見るのではなく違う角度から観察してみる事が大切です。
陰を作りそうな雑草はそのまま育ててみる

雑草内でも生存競争が激しく行われているのをご存知でしょうか。

大きな葉を横に広げる雑草は、自分の陣地をどれだけ横に広く確保できるのかが大切になってきます。
一方、高さが出る雑草は地表面では戦わず他の葉の少しの隙間から上へ伸び光を浴びることが大切になってくるのです。

大きな葉の雑草は、葉を広げることで陰を作り他の雑草の光合成を妨げることで他の雑草が生えなくなります。
そして、自分だけが悠々と生き残っていける訳です。

わが家は、アジュガとクリーピングタイムでカバー出来ない土のエリアをオオバコが覆っています。
オオバコは幼少期から慣れ親しんでいるからこそ根っこから抜きにくい事は知っていたので、当初は見つけた瞬間に殺気立ってしまいました。

初めは抜きやすい雨の日に除草していたのですが、それでもキレイに抜けません。
ストレスを抱えつつそんな事を繰り返すうちに、オオバコの葉の下には他の雑草が生えていない事に気が付きました。
どうやらオオバコの大きな葉が雑草対策をしてくれていたのです。

この出来事がキッカケで、雑草=邪魔者というネガティブなイメージが無くなりました。
それまでは除草する事ばかり考えていましたが「雑草の生命力を生かす庭管理もアリだな。」と前向きに捉えられるようになったのです。
種を付けさせない

種を付ける雑草は一年草に多く、子孫繁栄のために花が咲き種を付けやがて種がこぼれ翌年に向けて準備をします。
可憐で可愛らしい花を付ける一年草が、まさか爆発的な繁殖力を持つなんて想像出来ませんよね。
さらに、可憐な可愛らしい花を見ていると除草しにくい印象があります。
しかし、可愛らしい花に同情しているとやがて種を付けてしまいます。

増やしたくない雑草で花が付いた場合には、花が咲いた時点で花だけでもいいので取りましょう。
花を取ることで種が出来なくなるので、翌年以降は徐々に減っていきます。
逆に、可愛らしい小花がお好みであればそのまま放置するのもありでしょう。
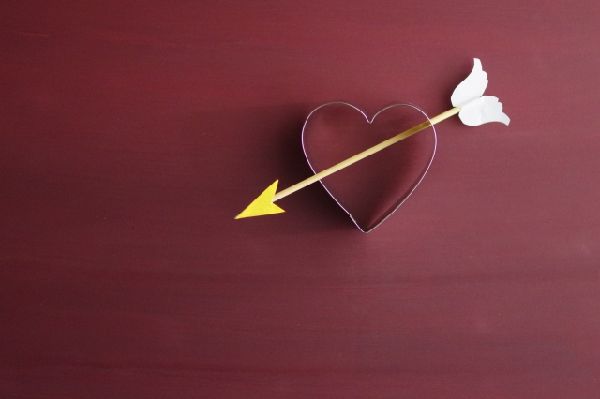
一年草雑草の凄まじい生命力は、長い月日を経て人間の心理を揺るがす「可憐で可愛らしい花作戦」を習得しました。
惑わされないように、心を鬼にして花を摘む事に取り組みましょう。
生えて欲しくない雑草は葉っぱを取る

「根っこから抜けなかった!」
雑草との戦いで敗北感を感じるのは、こんな時ですよね。
しかし、根っこから取る必要なんて本当にあるのでしょうか。
答えは「根っこから全て抜く必要はない」という事です。

根っこからではなく、葉を取る事が除草への近道です。

雑草も含め、植物は土、水、温度、光の4つの要素が生きていくうえで必要になってきます。
葉から光を取り入れる事で根っこを太らせながら成長をしているので、葉を取り除く事で光合成が出来なくなります。
すると、根っこに栄養素が送れなくなるので根っこは次第に弱っていき最終的には枯れてしまいます。

雑草によっては抜きにくい根っこもありストレスの大きい作業でしたが、これからは根っこではなく葉を取る事を心がけましょう。
根っこなんて、もう気にしない。
これで、お庭管理のストレスがかなり軽減されると思います。
グランドカバーで雑草を見えなくする
①-1625384938.jpg)
画像の中に雑草のメヒシバが存在しているのですが、繁殖力のあるグランドカバーであるヒメイワダレソウを植える事でメヒシバが目立ちません。
雑草とグランドカバーが同化するので忙しい日常で雑草に目が行く事が無いでしょう。

目がいかず気にならないと言うのは、作業したいけど忙しい日々で手が回らないという方にとってはストレス自体を感じないので心にも余裕が出来ますよね。
さらに、グランドカバーの勢いで雑草が激減するか徐々に弱り無くなっていく場合もあります。
①-1625384938.jpg)
グランドカバーは、雑草対策を行いたい広さに合わせて成長が早いもの遅いものを選択をしましょう。
広い範囲であれば、成長が早いヒメイワダレソウやリシマキアなどがオススメです。
頻繁に足を踏み入れるようなエリアには踏圧に強いヒメイワダレソウ、踏み入る必要がないエリアであれば踏圧に弱いリシマキアでしょうか。
また、グランドカバーが植えた環境にピッタリと合い爆発的に増えてしまったり、逆に適さずにグランドカバーの役割を果たさない事もあるのでグランドカバーの成長を見守る必要もあります。

わが家では、斑入りグレコマをグランドカバーとして活用しています。
まずは、葉が大きめなので雑草対策に向いている事。
次に、斑入りという事で同じグリーンの中でも明るめのライムグリーンがアクセントになり、お庭全体が明るくなるからです。

日向では爆発的に成長しているので、定期的に伸びて欲しいエリアへの誘因と剪定を行っています。
日陰~陰では枯れる事は無いですが観察している割には「本当に成長してる?」という位のスローペースです。

また、挿し芽も簡単なので自宅内の他の花壇などに試し植えも可能です。
その環境への適応力を見てから本格的に植えられるのでコスパが良いように思います。

全く雑草が無くなった訳ではないですが気が向いた時に目に付いた雑草を抜くだけで良くなりました。
また、グランドカバーによる一定の美しさがキープされているので雑多なお庭のイメージがないので心の余裕が違います。
腐葉土やウッドチップ、砂利などを活用する

山の中に雑草がないのをご存知でしょうか。
山の中では生い茂る高木に光が遮られて地面に光が当たらない為に、雑草が生きていけないのです。
また、落ち葉が堆積し雨が降り自然な腐葉土が堆積している事で、ますます土に光が当たらない事も大きな要因です。

そこで、みなさんのお庭も山の中のような環境を作ってみるのはどうでしょう。
落葉樹などを植えてみるのも良いですが、手軽な方法として腐葉土やウッドチップなどで地面を覆うという方法があります。

陰を作る面積にもよりますが、小さな面積であれば高価なウッドチップは見た目も良いでしょう。
広い場合には腐葉土を撒いていくのが良いかもしれません。
腐葉土は土壌改良にもなるので一石二鳥です。

わが家では、腐葉土と友人オススメのベラボンを併用しています。
ベラボンとは、 ヤシの実のスポンジ繊維を特殊加工したもので保水性がありつつ水捌けと通気性が良い植え込み材になります。
植物が元気に育つので土に変わる植え込み材として注目されているようですよ。
撒くだけなので簡易で素手で扱っても手が汚れない所が気に入っています。

また、場所によっては砂利などを引いて地面に光を当てない事も出来ます。
砂利を引く場合、砂利の大きさによっては隙間から光が入り雑草が出てくる事もあるので小さめの砂利で深さ5cmは引き詰めるのが良いでしょう。
雑草を庭の仲間にうまく取り入れて楽しい庭管理をしましょう

雑草のメリットを上手く活用する事で庭管理のサポーターになってくれる雑草達。
不要であれば、これまでのストレスの大きい対策ではなく簡単な雑草対策で除草できる事が分かりました。
ストレスのない雑草対策のポイント
・繁殖力の低い可愛らしい雑草は許容する
・雑草は、葉を取るだけでも大丈夫!
・時間がない時は花を摘み取るだけでも効果的
・グランドカバーを利用する
・ウッドチップなどを敷く(ベラボンがオススメです)
庭管理はストレスが大きければ長続きはしません。
雑草に振り廻されるのではなく、みなさんが雑草をコントロールして楽しい庭管理を心がけましょう。
関連記事
この記事のライター
九州在住のガーデニングライター
家作りをきっかけに庭管理を始めて12年。
関わってきた時間の分だけ、
植物の声が聞こえるようになりました。
子育てと似ていて上手くいかなかったり癒されたり!
難しく考えないで、
気になった植物に寄り添ってみてくださいね☆彡






.jpg)



.jpg)











