夏のお庭の水撒きをもっと楽に!
時間をかけない簡単な水撒き方法
水撒きに時間をかけない方法で、庭木も人も生き生きと過ごせる夏を!
-1627861941.jpg)
猛暑の夏が当たり前になりつつある中で、人間だけではなくお庭の庭木にも過酷な環境となりつつあります。
忙しい毎日の中で、ふと、お庭へ水撒きする事が頭をよぎりますが、朝から気温が上がり日没後まで続くとなると憂鬱になりますよね。
憂鬱な理由は、お庭全体に水撒きを行うのに要する時間や夕方のハードスケジュールの中で水撒きに割く時間がないなど様々だと思います。
しかし、そんな悩みが無くなれば、水撒きに対するハードルは一気に下がるのではないでしょうか。
今回、猛暑も時間も気にならず、お庭の水撒きを楽に行える方法をご紹介します。
この記事は、お忙しい方のために
目次の見出しを追うだけでも内容を理解できるようにしています。
詳しく知りたい方は、このまま読み進めていただくか
気になる小見出しをクリックしてみてください。
目次
庭木の水枯れサインを見逃さないようにしよう

みなさんが、水撒きを意識するのはどんな時でしょうか。
太陽がカンカン照りの時、毎日見かける玄関前の花壇の花がくたびれていた時、運転中に何げに見た水撒きのシーンなど、それぞれだと思います。
しかし、何かしらの水撒き指標があれば、大切に育てていらっしゃる庭木の水枯れを防ぐ事が出来ます。
猛暑に負けず緑色の葉を付け生き生きとしている庭木の姿は、この厳しい暑さの環境の中で私達の気持ちを穏やかにしてくれるでしょう。
早速、庭木の水撒きサインをご紹介をいたしますね。
紅葉している葉

数年前から感じている事ですが、まだ夏でありながら、紅葉していたり落葉している庭木を多く見かけるようになりました。
街中の桂の木などが黄色に変色している様子は、紅葉時期が秋から夏へと変化してしまったのかな、と思ってしまう位です。
しかし、これは明らかな水分不足です。

地中の根に水分を貯め込んでいる木は、状況に応じて地上の幹にも水分を送り込んでバランスを保っています。
さらに、葉は光合成を行うために気孔から二酸化炭素を吸収する役割を担っています。

しかし、猛暑などで葉に強い日差しが当たり過ぎると葉自体が熱くなり、光合成が出来なくなるのです。
そこで葉は、気孔から水を蒸発させ温度調整を行う事で、葉の温度を下げようとします。
もちろん、猛暑で水分不足を体感しているのは根も同じです。
根が吸い上げる水が不足している上に、地上部の葉は気孔から水を蒸発させている。
これでは、木自体が枯れてしまいます。
そこで、木は自ら葉を落とす事で水分の蒸発を抑えて身を守ります。
①-1627861941.jpg)
葉の色が黄色くなる原因。
それは、猛暑の中で木の成長の要である根を最優先した事で、光合成も出来ず熱くなった葉が水分不足というサインを出しているのです。
最近では、茶色にまで変色し踏むと粉々になってしまう落葉した桜の葉を見かける事が多くなりました。
葉の色が黄色になったら、明らかな水分不足のサインだと認識しましょう。
幹がカサカサしている

普段から、木の全体像や葉などには意識がいくと思いますが、幹の状態を観察する事は少ないと思います。
しかし、猛暑続きの夏の間だけでも幹にも注目してあげましょう。

2021年の夏至は6月21日でした。
1ヶ月以上経ち太陽の位置は少しづつ低くなっているので、日差しが幹にも直接届きやすくなっています。
幹に日差しが直接当たれば、幹自体が温まってしまいます。
平常であれば、根に蓄えられた水分が幹を通る際に幹自体が冷やされるので、幹の温度も下がります。

しかし、猛暑続きで水分不足になると、根は自分の水分を確保するために幹への水分供給を減らします。
それによって、幹を通る水分が減少する事で幹の温度が上がりっぱなしになり、幹焼けを起こしてしまうのです。
樹皮が剥けてしまったり、幹の表面がデコボコしたりします。
樹皮がカサカサという印象なので、日頃から観察しておくと違いが分かると思います。
最悪の場合は枯れる原因にもなりますので、猛暑の時期は幹の事も意識しておきましょう。
土が乾いている

土が乾いているのは、見た目で分かりやすいですよね。
乾いている土を見て「これは、水撒きのタイミングかも。」と思われる方が多いのではないでしょうか。
庭木の水撒き方法
根元にタップリ

みなさんは、どのように庭木に水撒きをされていますか。
庭木を目の前に何となくホースの水を撒いている、カラカラになった葉が目に留まり届く範囲で木の上部にも水を撒いているなど、様々だと思います。

しかし、前述したように、水分を最も行き渡らせる必要があるのは木の根になります。
水分を、根の部分に送る事が大切なのです。
それならば、どのような水撒き方法が効果的なんでしょうか。
①-1627861941.jpg)
幹元にホースを当てて、水量チョロチョロでしばらく置く。
これだけです。
気温が下がらないままの蒸し暑い夕方に、汗を流しながらホースを持って庭中の庭木巡りをする必要はありません。

水量を少な目にしながら幹の部分に置きっぱなしにするのは、一定の時間を使いピンポイントで根に水を送るためです。
注意点として、水量が多いと周囲に流れてしまい根に行き渡る水量の効果が期待できません。
しばらく流してみて、水が幹周囲に流れず留まるような状態がベストです。
どうしても流れてしまう場合には、幹元周囲の土を取り除き水が溜まるようなクボミを作ってあげると良いでしょう。
慣れてくれば、筆者のように自宅の水栓のひねり具合で水量が分かるようになります。
庭に出て、ホースを幹元に置き水栓をひねれば作業は終わるのです。

後は、数時間毎にホースの位置を気になる庭木の幹元に置き換えていくだけなので、自分の時間を取られずに済みます。
在宅中に朝から始めれば、5本位の庭木の水撒きが可能です。
たまに置き換えを忘れる事もありますが「今日はタップリ上げられた!」と前向きに考えましょう。
わが家は、夏になると水道使用量チェックの方に「今月、水道量が多いですけど。」と声を掛けられます。
2千円前後オーバーしますが、期間限定である事と、それで庭木が元気に生き生きとなれば安いものだと割り切っています。
水撒きの時間は気にしなくても大丈夫

今回ご紹介している木の幹元だけに水を与える方法なら、時間帯は気にしなくても大丈夫です。

ただ、その庭木の幹元周辺に何もなく、土が剥き出しで日射しが直接当たるようであれば、かえって逆効果になってしまいます。
ぬるま湯を与えることになるので、根を痛める原因になりかねません。

幹元周辺に何もない場合には、日射し対策は必要です。
長い目で考えると、手間のかからないグランドカバーや幹元が隠れる位の植物などを植栽されると良いでしょう。
時間がない方は、バークチップやベラボンなどで覆う方法もありますし、コストを掛けたくない場合には、落ち葉を集めて幹元をカバーするだけでも違いますよ。
水撒きを意識した方が良い庭木

夏の日差しに弱いとされている代表的な庭木は、桂、イロハモミジ、ナナツバキ、ヒメシャラなどです。
そのような庭木は、大体が午前中だけ日射しが当たる東側に植栽されている事が多いと思います。
西日は避けられますが、朝から日射しが厳しく気温上昇が当たり前の近年では、東側と言っても安心してはいけません。
水撒きの時間を長くしたり、水を与える頻度を他の庭木より多めにしてあげましょう。
時間はかけず庭木への愛情はタップリかけられる簡単な水撒き方法を取り入れましょう!
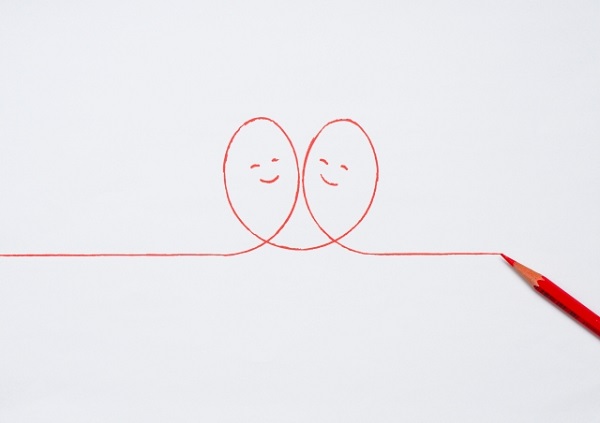
時間をかけない庭木への水撒き方法、いかがだったでしょうか。
ホースは持たず庭木の幹元に置くだけなので、自分の時間が奪われる事がありません。
庭木に意識さえ向けておけば、自分主体で行動できるので、これまでのような猛暑のお庭で蚊と汗に格闘しながら水撒きを行う必要はないのです。
長くお付き合いしていく庭木であればこそ、時間をかけない楽な水撒き方法を取り入れる事で、愛情がどんどん溢れていく事でしょう。
この記事のライター
九州在住のガーデニングライター
家作りをきっかけに庭管理を始めて12年。
関わってきた時間の分だけ、
植物の声が聞こえるようになりました。
子育てと似ていて上手くいかなかったり癒されたり!
難しく考えないで、
気になった植物に寄り添ってみてくださいね☆彡

















